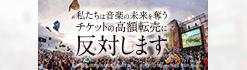GARY CLARK JR./ゲイリー・クラーク・ジュニア

NEWS 最新情報
-
GARY CLARK JR. 12年ぶりの単独来日公演を前にオフィシャル・インタビューが到着!2025.01.10
<次のヘンドリックス>とか<ブルースの新星>みたいに言われるのは、嬉しいと同時に
「自分は一つのことしかできない人間じゃないぜ」という気持ちがあった。
 2025年4月、東京・大阪の2都市で12年ぶりとなる日本での単独公演を行うゲイリー・クラーク・ジュニア。デビュー前からエリック・クラプトンによって『クロスロード・ギター・フェスティヴァル』のステージに抜擢されたことをはじめ、若かり日から多くのレジェンド達との関係性を築き、確かなキャリアを歩んできたゲイリー。ブルースをルーツに持ちながらも様々なジャンルを取り込み自身の音楽性を最大化させた最新アルバム『JPEG RAW』を24年にリリースするなどミュージック・シーンで確かな存在感を示す彼に偉大な先輩達との関わりをはじめとしたこれまでのキャリア、そして今回の来日ツアーなどについて話を聞いた。text:Yasufumi Amatatsuinterview & translation:Kyoko MaruyamaQ: 単独では12年ぶりの来日公演になりますね。前回は、話題の若手ギタリストとしてデビューした直後であなたも確かまだ20代でした。その時のことを覚えていますか。また、この間のご自分をふりかえってどんな感想を持たれていますか。
2025年4月、東京・大阪の2都市で12年ぶりとなる日本での単独公演を行うゲイリー・クラーク・ジュニア。デビュー前からエリック・クラプトンによって『クロスロード・ギター・フェスティヴァル』のステージに抜擢されたことをはじめ、若かり日から多くのレジェンド達との関係性を築き、確かなキャリアを歩んできたゲイリー。ブルースをルーツに持ちながらも様々なジャンルを取り込み自身の音楽性を最大化させた最新アルバム『JPEG RAW』を24年にリリースするなどミュージック・シーンで確かな存在感を示す彼に偉大な先輩達との関わりをはじめとしたこれまでのキャリア、そして今回の来日ツアーなどについて話を聞いた。text:Yasufumi Amatatsuinterview & translation:Kyoko MaruyamaQ: 単独では12年ぶりの来日公演になりますね。前回は、話題の若手ギタリストとしてデビューした直後であなたも確かまだ20代でした。その時のことを覚えていますか。また、この間のご自分をふりかえってどんな感想を持たれていますか。
Gary(以下、G): 20代を覚えているかって、大昔の話みたいじゃないか(笑)。いや、確かにひと昔だよね。あのツアーはウィスキーの会社がスポンサーで、夜通し飲むような日が多かった。だから、記憶はちょっと曖昧なんだ。でも、ものすごく興奮していたことは覚えてるよ。その日本での思い出も含めて、初めて見る世界が、しかもすごいスピードで一気に押し寄せてきた。初めて会う人、初めて訪れる場所、初めての経験ばかりだった。ステージが大きくなればなるほど、音量を上げなきゃならないわけだけど、そうするとハウリングを起こしてしまう。「このフェンダーの、もしくはエピフォン・カジノのホロウボディのハウリングを止めるにはどうしたらいいんだろう?こういう音色を出すにはどうすればいいんだろう?」と、ステージの上で、その場その場で正解を見つけながらやっていたよ。その頃は、人前に出るのがあまり得意じゃなくてね、インタビューも怖かった。カメラが向けられるたびガタガタ震えてたよ。パーティに行けば、テレビで見てた人に次々と会うんだ。アリシア・キーズがスウィズ・ビーツと一緒にいたり、マーティン・スコセッシがいたりとかね。何もかもが一気に起こっているようだった。
Q: この12年で、ブルース・ギタリストという括りから、広い意味でのアーティストに成長されたと思うのですが、自分でもそのような自覚はありますか。
G: そうだね。でも、自分としては、やりたいことはデビューした頃から、ずっと一緒だったと思う。オーストラリアを訪れた時、<次のジミ・ヘンドリックス>と言われているのを知って、そんなふうに言われるのは有難いと同時に、「やめてくれ」と思ったのを覚えている。そういう決めつけはされたくなかったからね。だって「Things Are Changin'」みたいな曲は昔からずっとやってたんだ。R&B風の曲にしてもそうさ。プリンスからの影響もあったし、90年代のヒップホップに影響を受けたビートもやっていた。ジャーメイン・デュプリ、テディ・ライリー、ベイビーフェイス、DJ マイケル・ワッツ、DJスクリュー、ダンジョン・ファミリー、クインシー・ジョーンズ等々。R&B、ブルース、ファンク、ロックンロール、レゲエとジャンルに関係なく、音楽が作られる過程そのものが好きだった。8歳とか9歳くらいには、ギター、ベース、ドラムをカシオのキーボードで重ねて音楽を作っていたよ。だから<次のヘンドリックス>とか<ブルースの新星>みたいに言われるのは、嬉しいと同時に「自分は一つのことしかできない人間じゃないぜ」という気持ちがあった。ぼくがブルース以外のことをやるのを聴いて驚く人たちもいるかもしれないが、アルバムに収められた12曲程度は、ぼくがこれまで演奏してきた何百万時間もの音楽のごく一部でしかない。もちろん、ブルースは常にぼくの一部だったし、土台だった。ブルース、R&B、ゴスペルこそがぼくの原点だ。その後、さらにいろんな音楽から影響を受け、それがぼくのプレイに染み込んできた。今後もそうあり続けるだろうし、やれなくなるまで、このまま進み続けるだけだよ。Q: 今回は、特に日本のファンにどんなところを注目してみて欲しいですか。バンドの編成についても教えてください。
G: 前回、日本のみんなにみてもらった時からバンドはスケールアップしているよ。ドラムはJ.J.ジョンソン、ベースにイライジャ・フォード、ギターのザパタは高校時代からずっと一緒だ。バック・ヴォーカルにぼくの姉と妹が参加してくれる。このメンツで何を期待できるかといったら、ブルース、ソウル、ファンク、R&Bのショーさ。ギターリックやスムーズなヴォーカル、ファンキーなグルーヴ、スウィングするビート、踊って、一緒に歌って、願わくば、少し考えるきっかけになってくれたらいいなと思う。楽しい時間を過ごしてもらえるはずさ。Q: 2010年のクロスロード・ギター・フェスティヴァルで、デビュー前のあなたは鮮烈な印象を残しました。今回映像化された2023年のフェスにも出演なさってますが、あのフェスティヴァルは、あなたにとってどんな存在ですか。
G: 文字通り、クロスロード・フェスはぼくの人生そのものを変えてくれた。2010年のシカゴで、エリック・クラプトンがぼくにくれた数分のチャンス、ドイル・ブラムホールが隣にいて、B.B.キングやバディ・ガイと演奏したんだ。あの時の話をするたびに、いまだに胸がいっぱいになって言葉に詰まる。1996年に初めてギターを手にして以来、ぼくはずっと「ああいうミュージシャンの一人になりたい!」と思ってきた。その全員が、初めて出たクロスロードのフィナーレのステージにいたんだ。ロス・ロボス、デレク・トラックス、スーザン・テデスキ、ロバート・クレイ、ヒューバート・サムリン、ジミー・ヴォーン、ジョン・メイヤー、バディ・ガイ、、、。ステージでB.B.キングがぼくの手を掴み、目を見て何か言ったんだ。でも、騒がしくて何を言われたのか聞き取れなかった。きっと「Welcome to the club, kid(お前もこれで一人前だ)」と言ってくれたんだと信じてる。あの日、ぼくは認められたんだと思う。あの日を境に人生は変わった。クロスロード・フェスティバルの意義や目的、そしてその基盤となる音楽を考えると、自分がその一部を担っていることが誇らしいよ。だって、クロスロード・フェスは本当に多くの人を助けているんだ。音楽業界でこうしたことを実現しようとしても、決して簡単ではない。ぼく自身、仕事や私生活において、いい時も悪い時もあったし、苦しんでもがいた時期もあった。でも、そこに行けば助けが得られる場所があるというのは、とても安心できるし、ミュージシャンが必要な支援を受けられる場所があるのは素晴らしいことだと思う。そんなチャリティーのためのクロスロード・フェスでキャリアをスタートできたこと、美しい機会を得られたことは、大きな意味があるんだ。この世の中でどう生きていくかを考えさせてくれた。チャンスは、自分のためにはもちろんのこと、手にしたなら、他の誰かのためにそれを活かすことが大切なんだと教えられた。とんでもなく答えが長くなってしまったけど(笑)、それくらいクロスロード・フェスティバルは特別なんだ。何度も参加させてもらい、クラプトンはもちろんだけどクルーたちとも信頼関係を築き、偉大なレジェンドたちと共にステージに立てることを、心から誇りに思っているよ。これまでの人生でやってきたことは、すべてクロスロードのようなフェスティバルに参加するためだったんだと感じる。つまり、「自分は間違っていなかったんだ」と、どこかで確認できたような気がするんだ。Q: エリック・クラプトンはあなたにとってどんな存在ですか。
G: 「ワオーッ」だね!最初のエリックのアルバムは親父からもらったんだ。まずは近所の人からもらったスティーヴィ・レイ・ヴォーンとジミ・ヘンドリックスのアルバムがあって、そしたら親父が「ギタープレイヤーになりたいなら、これを聴け。ギターっていうのはこうやって弾くんだ」と渡してくれたのが、サンタナ、そしてエリック・クラプトンの『ピルグリム』だった。親父と車の中で聴いて、夢中になったのを覚えているよ。「なんて新しいんだ」と思った。ドラムビートやシンセを取り入れたサウンドは、1996年当時、12歳だったヒップホップ好きのぼくにも共感できるものだった。「ギターレジェンドなのにアーバンなヒップホップ風ビートを使ってる。ローランドの808(ドラムマシン)の上にスライドギターを弾くなんてことをしてもいいんだ」と、その時、初めて知ったのさ。「ぼくにぴったりじゃないか」と。それ以前のクリームやデレク&ザ・ドミノズについては何も知らなかったが、その時クラプトンに出会えたことは、ぼくにとって最高のタイミングだった。大きな影響を受けたよ。Q: 2023年のフェスティヴァルでは、ジミー・ヴォーンと「Texas Flood」で共演してましたが、同郷オースティンの先輩とあの曲を共演することは、あなたにとって特別なことではないですか。
G: ジミー・ヴォーンと共演することはいつだって特別なことさ。ジミーはまだ高校を卒業したばかりだったぼくをツアーに連れて行ってくれたんだ。あれが初めてのツアーだった。ジミー・ヴォーンと共演する時はいつだって、キング・ジェームズ(註:NBAプレイヤー、レブロン・ジェームズ?)とやるようなもんさ。地元じゃ、ぼくらは彼をそう呼んでた(笑)。そんなジミーとエリック・クラプトンとクロスロード・フェスで「Texas Flood」を演奏できたなんて、テキサス出身の人間からすれば出来すぎじゃないか。それ以上、何が望めるっていうんだい、完璧だったよ。Q: テキサスの中でも特にオースティンは音楽の街、それもライヴの盛んな町として知られていますね。バーが立ち並ぶ6thストリートには音楽が溢れているし、SXSW、Austin City Limitsなど、若手のミュージシャンたちにとって未来へのチャンスの場となっています。そんなライヴ・ミュージックの都オースティンで育ったことは、あなたの人生にどんな影響をもたらしていますか。
G: 初めて6thストリートを歩いた時、オースティンの特別な空気を感じたよ。高校1年の時、友達のイヴの希望で、彼女の15歳の誕生日にブルースのジャムセッションに出かけたんだ。ぼくはそんな場所の存在も知らなかった。間抜けな顔をした、歯の矯正も取れない、ガリガリで、髪も服もぼさぼさの痩せっぽっちの10代のガキが4人、楽器を持って、当時はまだ許されていたタバコの煙が立ち込めるバーに入っていったんだ。すると年上のミュージシャンたちが、「お前ら、こっちへ来て一緒に演奏しよう」と声をかけてくれた。そんなことができるなんて知らなかった。もし知ってたら、もっと前に来てたね。自転車に乗れなくたって、木登りができなくたっていい。ABCを覚えるより先に、ギターを持ってこのバーに来て、ジャムセッションをしていたと思うよ。6thストリートを歩くとレゲエ、カントリー、ロックンロール、ロカビリー、パンク、メタル、あらゆる音楽が聞こえてきた。「なんだこれは!」と驚いたよ。高校生のバンドも演奏していた。バーに行って、手にXの印をつけてもらい、友達のバンドが出演するのを見た。もしオースティンで育っていなかったら、自分から音楽を探す一歩を踏み出すことはなかっただろうし、見つけるのは難しかったはずだ。でもオースティンにいたから、フラッと歩いて入っていけたんだ。そこは、まるで魔法のようで、誰もが若いぼくらを暖かく迎え入れてくれた。彼らはぼくらを育ててくれた。正しい道に導いてくれる人もいれば、間違った道に引っ張ろうとした人もいた。そうやって、若いうちから貴重な経験や機会の場に触れることができたんだ。つくづく、当時のオースティンでしか得られない特別なものだったと思うよ。Q: その後も、チャック・ベリー、B.B.キング、ローリング・ストーンズ、もちろん、エリック・クラプトンなど、レジェンドと呼ばれる先輩たちと数多く共演し、彼らにとても大事にされてきたように思えます。それはあなたが、彼らが創ってきた伝統を引き継ぎ、そこに革新を注いで次の世代へと繋いでいく存在だという期待があるからではないかと思うのですが、あなた自身、そんな先輩たちの期待についてどう感じていますか。
G: そのことを考える時、いつもクリフォード・アントンを思い出す。彼はオースティンにあるクラブ「Anton’s」の伝説の経営者だ。まだ子供だったぼくを彼は出演させてくれて、レジェンドたちのステージにも立たせてくれた。そして「ゲイリー・クラークこそ、ブルースの未来だ。そんなゲイリー・クラークに拍手を!」と、毎回紹介してくれていた。ある時、オリジナルの「Things Are Changin'」を演奏していたら、クリフがステージに近づいてきて「ジミー・リードの曲をやれ」と言ったんだ。ジミー・リードは言うまでもなく、史上最高の伝説のブルース・アーティストだ。ぼくは笑って返したが、心の中ではこう思った。「やるよ、クリフ、やるとも。でも同時にぼくは自分の曲を自分のやり方でやる」とね。つまり、「自分がどこへ向かっているかを忘れるな。そしてどこから来たのかも忘れるな。さらには、自分が向かう道の邪魔を他人にさせるな」ということ。ルーツは心からリスペクトするさ。でも、ぼくには他にもやらなきゃならないことがあるんだ。>続きを読むスティーヴィーから連絡をもらうのは、「君を自分の生徒として認めているよ」と言われるようなもの