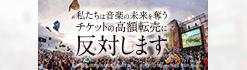Q: 新作『JPEG RAW』は、音楽的にも、社会的にも、素晴らしく野心的なアルバムのように感じます。音楽的には、ブルース、ジャズ、R&B、ワールド、ヒップホップと広がり、サンプリングを多用したり、多彩なアイディアとテクノロジーが駆使されています。と同時に、混沌として不安定な現代社会に対するあなたのメッセージも伝わります。このアルバムで表現しようとしたことを教えてください。
G: きらびやかで華やかなパーティのようなアルバムが溢れる世界の中にも、静かで孤独で内省的な音楽はあるんだ、ということかな。このアルバムは一種のセルフィ(自撮り)、つまり、鏡の中を覗いて「これが自分なんだ」と思う感じさ。良い面も悪い面も醜い面も含めて全部ね。ライトが消えて、カメラが止まった時に浮かび上がってくるもの、そんな曲ばかりだよ。たとえば「Triumph」は自分の子供たちに本音で語るとしたら、何を語るか。彼らが耳を傾けるべきは何か。「To The End of the Earth」から「Alone Together」へ続く流れは、愛は最初おとぎ話のハネムーン期みたいだけど、炎みたいなもので、ちゃんと手をかけていないといつか消えてしまう、というようなね。アルバムを通しては、リアルで生々しいブルース・アルバムだと言っていいよ。現代のテクノロジーを使いつつも、やってることはローダウン・ブルースなんだ。
Q: アルバムで駆使された新しいアイディアやテクノロジーを、ライヴでどのように再現、もしくは変えようと考えていますか。
G:(サンプリングなどの)トリガーを使って、すでに試しているよ。それが楽しくもあるが、制約になることもある。なので、制約になることはなるべく取り外し、完全な生音で再現する方向に今は向かっているところだ。つまり、アルバムでは機械がやってたことをライヴで人間が代わりにやるにはどうすればいいか。そうすることでまたアルバムとは全然違う、別の会話が生まれてくるだろうね。
Q: スティーヴィー・ワンダーとはどういう経緯で一緒にやることになったのですか。彼はあなたにとってどんな存在ですか。
G: スティーヴィー・ワンダーの声は生まれた時からずっと聴いてきた。おそらく今、地球上に存在する多くのミュージシャンがここにいる原因の一つがスティーヴィーなんじゃないかな。スティーヴィーのおかげで音楽に恋をし、ミュージシャンになりたいと思った人間が大勢いるに違いない。もうだいぶ前になるが、スティーヴィーのグラミー・トリビュート・コンサートでビヨンセとエド・シーランと(「Higher Ground」を)やったこともあるし、(スーパーボウル)ハーフタイムショーのステージに呼んでもらって、一緒にパフォーマンスをしたこともある。そんなふうに何年にもわたって交流はあったんだよ。パンデミックの間にスティーヴィーから連絡をもらい、一緒にやりたい曲があると言われた。もちろん、こちらとしては光栄極まりない話だ。スティーヴィーから連絡をもらうのは、「君を自分の生徒として認めているよ」と言われるようなもので、ようやく黒帯をもらえた気がした。リレーのトーチを手渡しされた、というかね。言葉でどう説明していいかわからないんだ。だって、ぼくのソングライティングにスティーヴィー・ワンダーの影響は本当に大きかったんだ。ジミー・リードの12小節のブルースから、どうやって可能性を広げて行けばいいのか、そう思った時にスティーヴィー・ワンダーを聴いて、答えをだしていたわけだからね。夢を持ち、それを叶えたいと願ってきた者にとって、毎日が感謝の気持ちでいっぱいだし、こうやって声に出してそのことを話すたびに、なんだか現実とは思えないような不思議な気持ちになるんだよ。
Q: 映画『エルヴィス』に、アーサー・ビッグボーイ・クルーダップ役で出演していましたが、その時の話を聞かせてください。あと、エルヴィス・プレスリーに対する思いもあれば教えてください。
G: バズ・ラーマン監督から連絡があったんだ。物語の語り方というだけでなく、ビジュアル面も含め、素晴らしい作品だった。当然、アーサー・ビッグボーイ・クルーダップ役で声がかかり、嬉しかったよ。エルヴィスが歌って有名にした「That’s All Right」の作者だ。エルヴィスが彼の解釈で歌い、大ヒットさせた。バズがあの曲を映画に入れたことは本当に重要だと思ったし、彼がそのルーツをしっかりと伝えてくれたことに心から称賛を送りたいよ。昔の音楽業界では、こういう人たちに対する正当な評価はずっとされないままだった。ブルース・アーティストやソングライターたちの書いた曲が、ある日突然、スターによってカヴァーされ、大ヒットした。でも、作者や元のアーティストの存在は誰も知らないままのことが多かった。契約的にも金銭的にも、不公平な扱いを受けて終わってきたんだ。だから、そんなシーンで出られたのはとても良かったよ。撮影はオーストラリアだったが、ビール・ストリートやメンフィスの街並みのセットが再現されたんだ。俳優たちも実はアメリカ人は少なくて、アフリカ人やオーストラリア人が多かった。演じている時は、メンフィスや南部の訛りや方言で話すのに、カットがかかると、みんなまるで違うアクセントで話すんだよ。本物の南部出身のアメリカ人であるぼくが見ても、オーストラリアでメンフィスが完全再現されているのは、いかに製作陣や俳優たちが、プロの仕事をしているのかがわかる面白い体験だった。映画の中における音楽の扱われ方もとても良かったと思うよ。そして何より、エルヴィスを演じたオースティン・バトラーが素晴らしかった。会う前から「オースティンは今、オースティンじゃない。エルヴィスだ」と言われてたんで、彼に会う時は「キング」と呼ぶようにしていた。「キング、調子はどう?」と。一度もオースティンと呼んだことはなかったよ。だから、こちらもカメラが回る前から、ゲイリー・クラークとしてではなく、アーサー・ビッグボーイ・クルーダップとして役に入り込めたんだ。彼といる時は今の時代の話は一切せず、ただ音楽の話、古いブルース・プレイヤーたちの話、そして彼の衣装について話した。あれは滅多にできない素晴らしい経験だったよ。
ーーありがとうございました。4月の来日公演楽しみにしています。