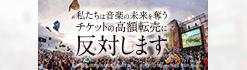JOURNEY/ジャーニー

NEWS 最新情報
-
JOURNEY ジャーニー、結成50周年記念の 日本ツアーが大阪から開幕!2024.10.20
※セットリスト・曲名には触れておりません。
開演予定時刻とほぼ同時に客電が落ち、ニール・ショーンが姿を現す。ひとりギターをかき鳴らし始めると、それがこの夜の始まりの合図だった。短いソロを弾き終えると、そのままショーンのギターからブライトなアルペジオが奏でられる。続いてアーネル・ピネダが最初のフレーズを歌い出すと、アリーナは一気にジャーニーの色に染まった。
ジャーニーの結成50周年を記念したツアー“フリーダム”、日本公演は秋の大阪からスタートした。オープニングから人気曲が披露され、アリーナとスタンドを埋め尽くしたファンは歓迎の意を表して大きく手を上げる。2007年に加入し、すでに17年も在籍するピネダは、今や押しも押されもせぬバンドのフロントマンだ。短い髪でさわやかな出で立ちの彼は、とにかくアクティヴ。曲の間奏ではステージ上手でソロを弾くショーンに絡んだかと思えば、次の瞬間には踵を返して下手に走り、観客を煽る。ステージで飛び跳ね、オーディエンスとのシンガロングを指揮する。アッパーな曲では、つねに笑顔を絶やさない。そんな彼が発する陽のエナジーで、アリーナ中にハッピーな空気が充満する。
この日は音響も際立っていた。ショーンがフルピッキングでこなす速弾きは音が明確に粒立ち、ギターを交換するたびにその個体が持つ個性を浮かび上がらせる。ディーン・カストロノヴォのドラムは、キック音をいたずらに強調させない。これを強くするとドライヴ感が増して勢い付く反面、ジャーニーの特徴であるメロディー、ハーモニーをスポイルさせてしまう。カストロノヴォの技術でそう演奏したところもあっただろうが、とにかく歌を聴かせることを最優先したバランスで整える。会場のAsueアリーナ大阪はスポーツアリーナであり、いわゆる“箱鳴り”は期待できない。ここでの公演の際はベースの音が埋もれてしまうこともあるが、今日はその存在を明確にし、アンサンブルを下支えしていることがはっきりとつかみ取れる。サウンドクルーは、良い仕事をした。今後の横浜、東京公演もコンサートホールの会場ではないが、ライブを楽しみにしている人は、この点にも期待してもらって構わないだろう。

このあとも公演が控えているので詳述は避けるが、セットリストには黄金期のナンバーが惜しげもなく並ぶ。結成50周年を迎えたとはいえ、'75年のデビューからしばらくは鳴かず飛ばずの状態だった。そんな彼らが成功への扉を開いたのは、“あの声”と出会ったこと。ボーカリストのスティーヴ・ペリーが加入して、新たなラインナップで発表した'78年の4th『インフィニティ』が初のプラチナディスクを獲得。ここで、“ジャーニーの型”が確立した。以降はそれを深化させ、'81年に今も最高傑作と称される『エスケイプ』が世に放たれる。しかしそれは、“ジャーニーの型”から逃れられない呪縛の始まりでもあった。ハードなサウンドとメロディアスな楽曲の上に、雑味なく透き通るようなハイトーンのボーカルが乗る。それが、“ジャーニーの型”。その点において、ペリーは重要人物であった。だが'83年の『フロンティアーズ』と、それにともなうツアーを終えるころからメンバーとの関係が悪化して活動は休止。それから10年の時を経て復活するも、長くは続かなかった。
その後、新たなシンガーにスティーブ・オージェリーが加入する。オージェリーはそれまで大きな成功を得られていなかったが、ペリーと近しいタイプのシンガーで、ジャーニーにマッチした。その証拠に在籍した8年間は定期的にツアーを行い、オリジナル・アルバム2作に参加。彼は良い仕事をしていたが、喉の不調が原因でバンドを離れてしまう。
ジャーニーは後任にイングヴェイ・マルムスティーンのバンドにも在籍していたジェフ・スコット・ソートを迎えるが、上手くはいかなかった。ハイトーンのボーカルがあれば、それでいいというものでないことが、この一件で明らかになったのだ。ソートの加入が実を結ばなかったことで、バンドは“ジャーニーの型”を守ることこそが生命線であると再認識した。


新たな後任探しは困難を極めたがある日、奇跡が起こる。ピネダが在籍していたバンドが、ウェブサイトにジャーニーのカヴァーをアップしていた動画が偶然、ショーンの目に留まった。それをきっかけに実施されたオーディションを経て、正式に加入が決定。フィリピンのローカルバンドのシンガーに過ぎなかったピネダはシンデレラストーリーを駆け上がり、世界的バンドのシンガーとして今、大阪のステージに立っている。
ショウはとにかく「ジャーニーのライブであるなら、この曲は演奏して然るべし」といったラインナップが並ぶ。ピネダはその声で、ジャーニーを今に存在させている。セットリストのなかで数曲、ほかのメンバーがリードボーカルを務める曲もある。それはかつてペリーが歌った曲であるのだが、彼らが歌っても全体の流れに澱みはない。たとえほかのメンバーに歌える力量があったとしても、“ジャーニーの型”から外れたタイプのボーカルであれば、その機会は用意されなかったことだろう。だからこそ、そのパートで違和感を覚えることはなく、むしろ良いアクセントになっていた。
後半は“これぞ!”なナンバーが、次々と飛び出した。硬軟交えながら、まさに怒濤の展開である。終盤に差し掛かっても、今のジャーニーの声に乱れはない。来日直前にブラジルで行われた音楽フェス「ロック・イン・リオ」に出演して、ピネダへの批判がSNSで渦巻いたとニュースになった。そのステージを現地で見たわけではないので直接の比較はできないが、この日の彼のボーカルには問題を感じなかった。中音域はふくよかで、高音はしっかりと伸びている。その印象が最後まで変わらなかったことは、強調しておきたい。
彼らはバンドの歴史のなかで、いくつかの奇跡と巡り合っている。ひとつめの奇跡は、“あの声”との出会い。ふたつ目の奇跡は、“新たなあの声”を発掘できたこと。そして3つ目の奇跡は、この夜に目にした。それは結成50周年を迎えたベテランバンドでありながら、全盛期のクオリティを保ったまま、フルスケールのショウを完遂したことだ。ジャーニーはここに集まったオーディエンスが求めているものを、なにひとつ欠くことなく提供してステージを終えた。アリーナをあとにする多くの観客が浮かべる満足気な表情が、それを物語っていた。

(取材・文/カワサキマサシ)
(写真/田浦ボン)
-
JOURNEY 会場で販売するグッズの一覧を公開!2024.10.17
-
JOURNEY ジョナサン・ケイン インタビューを公開!2024.07.16
Jonathan Cain Interview / ジョナサン・ケイン インタビュー
Q:バンド結成50周年を記念し、最新アルバム『Freedom』の名を冠した今回のツアーですが、日本公演はどのようなものになるか、ファンは何を期待できるか、ショーのハイライトは何になるか教えてください。
J:50年間に及ぶジャーニーの音楽を祝うツアーなのでね、『Infinity』から『Raised On Radio』までの旧譜、最新作の『Freedom』までを網羅し、ファン、そしてバンドのレガシーを祝福する公演になると思うよ。ジャーニーは50年間、音楽を一緒に作ってきたわけだが、50年というのは決して短くない年月だ。その50周年を日本に戻って祝えるなんて、ニールも僕も本当に光栄に思っているんだ。そして今回はMr.ウドーに敬意を表するという意味もある。彼がもういないのはとても残念だが、今回のツアーでは心からの敬意をMr.ウドーに表したいと思っているんだ。
Q:2017年以来7年ぶりの日本公演となりますが、日本で楽しみにしていることはありますか?
J:そうだなぁ(笑)なんといっても食事!そして酒、焼肉、コンサート終演後の真夜中のディナー。ウドーのスタッフがいつも連れて行ってくれて、深夜近くまで盛り上がるんだ。ウドー・チームとジャーニー・チームの間には兄弟のような絆があるからね。僕らが「これを食べよう」「あれをしたい」とどんなクレイジーなリクエストを出しても、「このステーキを食ってみろ!これはどう?」と次々と叶えてくれるんだ。僕は食べることが大好きなfoodieなんだ。酒にも目がない。Sake Boy って呼ばれて、純米吟醸酒をボトルで持ってきてくれる。お米を磨くとあんな美味しくなるとは知らなかった。日本の文化も大好きだ。初めて訪れた頃に比べ、日本が遂げた発展を考えると、すごいことだと思う。日本が灰の中から立ち上がり、世界の経済大国となり、アメリカの同盟国になったのは素晴らしいことだよ。
Q:コロナ禍を超えて、変わらずツアーを精力的に行っていますね。あなた自身にとって、またジャーニーというバンドにとって、ライブとはどのようなものですか。
J:ライブは僕らの命の源さ。コロナ禍、僕は「Hard To Let It Go」という曲を書いた。あれを聴いてもらえば、僕の心の声が聴こえると思う。あれは、僕らから奪われてしまったもののことを歌ったんだ。そして収められたのは最新作『Freedom』の日本盤だけだ。他の国では収められなかった。そうなったのには理由があると思う。僕は日本のファンのみんなに、どれだけ会えないことが寂しいかを伝えたかったんだ。あれは僕の個人的なメッセージだ。(コロナで、ツアーを)手放さなきゃならないのは、とても辛いことだった。でもそうするしかなかった。あの何ヶ月もの間は、辛い日々だったが、感謝する気持ちも教えられたよ。何かが奪われてしまった時は、その状況に寛大な心で、謙虚に、感謝をしながら立ち向かうしかない。日本のファンにとっても、僕らにとってもみな同じように辛い時期だった。「Hard To Let It Go」を聴いてもらえて、そんな僕の思いが伝わればいいなと願っているよ。
Q:そうやってまたツアーに戻られていますが、以前に比べ、今のあなたにとって音楽やコンサートの魅力は変わりましたか?
J:そうだな、ひとつだけ言えるのは、今のライブやツアーにおけるチケットの価格設定やチケット販売にまつわることに対して、そろそろ規制が必要だと思っているってこと。テイラー・スウィフトはそのことを率直に声をあげている1人だが、特にアメリカのチケット代は今、あまりに高騰しすぎている。ファンが来れなくなるような価格設定にならないように、僕らアーティストが注意しなければならない。そうじゃないと、ファンはライブから遠のいてしまうよ。ロックンロールの世界に公平さを取り戻さなきゃならないと思っている。ファンに対してもだ。日本ではそうではないと願いたいが、今アメリカでは調査が進められているよ。スポーツの世界に似てきたというか…たとえば、バスケットボール。父親が子供を何人か連れてNBAの試合を見に行こうと思っても、あまりに高すぎて手が出ないんだ。一家で行ったらいくらかかる?ジャーニーのライブを観にくるのに500ドル出さなきゃならないなんてことにならないように、ファンにフェアでないと。実際、アデルやテイラー・スウィフトのチケット代は1枚500ドルだ。そんな高額なチケット、誰にも買えなくなってしまう。そうならないように、スポーツ選手やエンタテイナーたちはファンにとって公平でいないと。今のチケット市場を見てて心配になるのはそこだ。家族4人でジャーニーを観に行けるような価格設定、そしてライヴを見終えて会場を後にする時、チケット代以上の体験ができたと思ってもらえるようでないとと思うんだ。
Q:2022年に11年ぶりにリリースした新作『Freedom』は、過去の焼き直しでない一段とパワーアップされた素晴らしい作品でした。11年振りにリリースされた背景はどのようなものなのでしょうか(ニールに昨日聞いたら、コロナ禍に曲を書き出したと言ってましたが)こちらのアルバムについて教えてください。
J:ああ、あれはすべてファイル共有で作ったアルバムだった。正直、変な感じだったよ。でも僕らはプロだからね。コロナ禍はやることがなくなったので、忙しくしているために作ったんだ。送られてきた曲を僕が完成させ、ほとんどの歌詞は僕が書いた。もし、歌詞が嫌いだって思う人がいたら、僕のせいだよ。正直、アルバムを作ることにすごく乗り気だったわけではない。でも世の中には、もっと最悪なCOVIDソングがいっぱいある。いくつもそういうのを耳にしたよ。それに比べ、「The Way We Used To Be」が書けた時には「これは最高のCOVID ソングだ」と思ったんだ。だが残念ながら、スティーヴ・スミスとロス・ヴァロリーとの裁判中だったので、リリースすることができなかった。それだけは悔やまれるよ。もしあれを僕が書いたときにシングルとしてリリースしきてたなら、アルバムにも大きく影響してたと思う。でも訴えられていたんでね、彼らに。
Q:そんな最高のチームであるジャーニーには、世代を超えた最高のファンがいますね。そのような幅広い世代の支持を得ている理由は何だと思いますか?
J:それは、僕らの書いた曲が“その世代を歌った曲”だったからさ。でも“小さな街に住む孤独な少女”(Just a small town girl livin’ in a lonely world〜「Don’t Stop Believin’」より)は今の時代にもいるし、彼女は“真夜中の列車に乗ってどこでもいいから行く”(take the midnight train going anywhere)ことを望んでいる。そして”サウスデトロイトで生まれ育った(born and raised in South Detroit)” 彼にしても、今でも“真夜中の列車に乗ってどこかへ行きたい”と思っている。ジャーニーが歌うのは、そんな希望と愛と可能性についてだ。僕らのファンに対しても「なんだって可能なんだ」と言ってきた。「そこから抜け出せないわけじゃないよ。真夜中の列車に乗ってどこへでも行ける」んだ。「信じることをやめないで(don't stop believing)」、そうすれば「愛に夢中になれる(stoned in love)」し、「両手を広げ(open arms)」た中に飛び込んでいける。もう「別々の道(separate ways)」を進まなくていいんだよ、と。だって何よりも大切なのは「自分にやさしくしよう(be good to yourself)」ってことだから。それが全てさ。僕らはただ“夢を見てもいいんだよ”ということを言いたいだけ。それがジャーニーのメッセージさ。「僕らは永遠に君たちと一緒だよ、誠実に(faithfully)」と。
Q:今後の予定は?夏、秋、来年…と何かありますか?
J:どうかな。ジャーニーとしては、ちょっと1年くらいは休むことになるかな。ここ5年くらい、本当に忙しく働いてきたんだ。日本には来ることができなかったけど、その間本当に忙しかった。なので、少し休み、そしてまた2025年にはツアーが始まることになるよ。(*とご本人は言ってますが、秋はデフ・レパードとのツアーがあるので、それを除いて、ということかと思います)
Q:最後にジャパン・ツアーに向けての意気込みと、日本のファンへメッセージをお願いします。
J:また日本に戻れることを本当に嬉しく思うし、僕らにその道を開いてくれたMr.ウドーにも心から感謝するよ。彼なしでは、日本に来る機会はなかったわけだし、Mr.ウドーとウドーの素晴らしいチームには、何年にもわたって本当に良くしてもらった。日本で一緒に再び火を灯し、思い出を呼び起こしたいよ。若い頃に聴き、人生のサウンドトラックになっている曲を聴いたなら、「まだ自分は生きている」「こんなに好きなものがあるんだ」という感覚や記憶が蘇るかもしれない。もしくは子供の頃に両親に聞かせてもらったこと、両親が君を信じてくれていたことなどを思い出すかもしれない。そしてあの素晴らしかった時代を思い出すかもしれない。ジャーニーは不安な時代に、皆が寄り添える安心できる音楽だ。今は本当に不安な時代なので、僕らの音楽が日本の人々の心を元気にしてくれるものであってほしいよ。
Q:ありがとうございました。
-
JOURNEY ニール・ショーン インタビューを公開!2024.07.16
Neal Schon Interview / ニール・ショーン インタビュー
Q:バンド結成50周年を記念し、最新アルバム『Freedom』の名を冠した今回のツアーですが、日本公演はどのようなものになるか、ファンは何を期待できるか、ショーのハイライトは何になるか教えてください。
Neil Schon:君がどの時代のジャーニーを見たんだとしても、これまで見たどれよりも、エネルギッシュなステージになることは期待してくれていいよ。僕も、バンドも、エネルギーだけはまだ失っちゃいないからね。まだ持ち続けている。ステージに上がった瞬間、スイッチが入って、最高の音楽が生まれてくるんだ。当然ながら『Freedom』からの新曲も演奏するだろう。実は何曲もリハーサルはしたのに、なぜかこれまで行った全米ツアーでは1〜2曲しか演奏できなかった。なので、日本ではどの曲を演奏することになるか、僕自身も楽しみなんだ。楽しいショーになることを期待してる。
Q:コロナ禍を超えて、変わらずツアーを精力的に行っていますね。あなた自身にとって、またジャーニーというバンドにとって、ライヴとはどのようなものですか。
N:僕にとって、ライヴは絶対に手放せないものだよ。スタジオに入って、何かを作るのももちろん大好きだが、ライヴを超えるものは何もないんだ。観客を前に音楽を演奏し、それがちゃんと伝わっていることが感じられる時、僕らは彼らをどこにでも連れて行ってあげられていると感じられるんだ。コンサートのさまざまな瞬間でね。それは音楽の旅、まさに音楽のジャーニーさ。そう思える時にものすごく大きな充実感を感じるよ。これは他では感じることがない感覚だし、これからもそれを超える感覚はないと思う。
Q:キャリアを重ねてこそ見えてきた、音楽の魅力、コンサートの魅力がありますか?
N:レパートリーが増えるに従って、演奏にしても、楽器にしても、僕が学べることには終わりがないなと感じるんだ。言ってみれば、頭の中で想像したことを、僕はいつまでも追い続けているんだ。曲を書くにしても、最初に想像できなければ何も書けない。そうだろ?今は昔大好きだったアーティストの音楽に戻って、聴くことが多いよ。ロックに限らず、例えばマイルス・デイヴィスの70年代や80年代前半の作品とか。今はそこら辺の音楽をよく聴いている。ジャーニーとは全然違うかもしれないけれど、誰もが十分に柔軟な考えを持って、それを許すなら、何かが起こるための場所はあるんだ。今、僕が夢見てるのはジャーニーがこれまでやって来たことを全て、最初から現在、そして未来までを一つにまとめて、形にすること。例えば、ラスヴェガスのスフィアのような会場でジャーニーがやる姿が、僕には想像できるんだ。まだ現地に行ったことはないんだけど、音楽と映像を駆使したあの会場でいろんなバンドがやっているのをYouTubeで見た。初めて見た瞬間から、「フィッシュやジャーニーがここでやる姿が想像できる」と思ったんだ。あそこでならビジュアルでまず世界に入り込み、そこから音楽へとさらに入っていくことができる。音楽を普段からいっぱい聴いて耳の肥えた人たちはともかく、ごく平均的な「ヒット曲は知っている」「ラジオでかかった曲は覚えている」という人たちにより音楽的な体験をしてもらうには、視覚も提供しないと。なので、あの会場のような本格的なアート体験を加えることで、音楽をさらに推し進めることができる。フィッシュを例に挙げたのは、たまたま前に彼らのライヴを見たことがあるからさ。あそこはマイルス・デイヴィスやジミ・ヘンドリックスといった60年代後半〜70年代のサイケデリック期のトリップ感のある音楽を見て、感じるのに最適だと思う。若い世代にとっては初めて知る新しい世界だ。その時代のバンドはもういないわけだから、僕らが時代を先に進めつつ、当時がどうだったか、その要素を捉えたことが何か出来たら、すごくおもしろいんじゃないかと思ってる。
Q:スフィアでのジャーニーを期待しています。
N:果たしてやれるか…やってみるさ!(笑)
Q:実に11年ぶりにリリースした新作『Freedom』は、過去の焼き直しでない一段とパワーアップされた素晴らしい作品でした。アルバムについて教えてください。
N:コロナ禍のロックダウン中に、自宅でキーボードを弾くようになったことがスタートさ。これまでもキーボードは弾いていたが、それほどではなかった。今回、KORGのキーボードにすごくいいドラムループがあって、それで最初に書いたのが「The Way We Used To Be」だった。それをジョナサンに送ったら、すぐにコーラスとヴァースを書いてくれた。最初はそれほど期待していなかったんだ。あまりジャーニーらしい曲調ではないと思ったからさ。だから曲が出来上がっていったことにすごく興奮して、そのままバンドのための新曲を書き続けていったんだ。でもメンバーの中には全く新しいことに挑戦する柔軟さがある者もいれば、これまでやったことの枠に留まる方が安全だと思う者もいる。でも僕は一歩先に進むためには、新しいものを作りたいと思った。レディオヘッドみたいなバンドを見るとそれを感じる。好き嫌いは別として、彼らは作り出すエネルギーはすごいと思う。リアルなんだ。そうやってリアルなものでなければならないと思う。ただ以前にうまく行った方程式を再現するだけじゃダメだ。「前にもこれでうまく行った。だからもう一回やらなきゃ」。いや、そんな必要はない。ヒット曲に似てるので、ライヴではもう演奏しなくなった曲はいっぱいあるよ。これ以上、そんな曲を増やしても意味がないと思う。これまでのジャーニーにはないタイプの、でも素晴らしい曲を作っていきたいんだ。
Q:ジャーニーというバンドは古くからのファンのみならず、若い世代のファンもいますね。世代を超えた支持を得ている理由は何だと思いますか。
N:彼ら(若い世代)が僕らの音楽を好きでいてくれるという事実こそが、その理由さ。それを目の当たりにしたのは、シカゴのフェスに出た時だ。えーーっとあれは…
Q:ロラパルーザ?
N:そうだ、ありがとよ。ロラパルーザに出たのはその時が初めてだし、それまでは声が掛かったこともなかった。ロラパルーザはどちらかというと、メインストリームのアクトはあまり出ない。で、僕らはいわゆるメインストリームだと思われているじゃないか。でもあの晩の僕たちに対する観客の反応は、とてもそんな感じではなかったよ。前から10列くらいを見ると10代くらいの若い子がぎっしりで、みんな歌詞も歌えるし、大盛り上がりなんだ。こちらが大胆になればなるほど、彼らはノってくる。「若い子は最高だ!」と思ったよ。彼らはどんなものを聴くのも恐れないし、ジャンルにこだわっていない。自分が知らないものは怖いから聴きたくない、ってことはないんだ。ジミ・ヘンドリックスが初めてアメリカで、モンタレー・ポップに出た時の様子が映像に残ってるが、あれを見ると、誰も彼が何をやってるか訳が分からず、あっけに取られて座ってるんだ。「怖がるべきなのか?いいと思うべきなのか?今度はギターを燃やしてるぞ。これは冒涜か?」と。でも前に、そして新しい時代に進むには、恐れててはいけないと思う。若い子たちは恐れていない。こちらが信じるものを提示すれば、彼らはそれを恐れずに聴いてくれる。でもその前に、まず僕ら自身が信じてなきゃだめなんだけどね。
Q:そうやって80年代の音楽が今も若い人に意味を持っているのは、曲自体にパワーがあったから?もしくは、今よりも楽天的な時代のせいでしょうか?
N:ジャーニーの歌詞は常に楽天的というか、前を向く歌詞だったと思う。政治のことを歌ったり、「こんなに俺は怒ってる。あいつを殺してやる」という、ダウナーなバンドだったことは一度もない。バンドは皆それぞれに違うので、いろんなバンドがいていいと思う。ジャーニーの歌はポジティヴだったというだけさ。でも確かに、楽曲自体は当時の方がよく書けていたね。今ラジオで耳にするのはどれも同じような曲ばかりだ。たとえ良い曲だったとしても、ものすごく新しいと感じられる曲にはめったに出会わない。所詮、音楽は良いか悪いか、耳をひくかひかないか、のどちらかなわけだが、良い音楽だったとしてもどこかで聴き覚えのある曲ばかりだ。僕は長くやってる分、歳を取ってる分、世界中のありとあらゆる偉大なミュージシャンやバンドを聴いてるんでね。自分なりの意見があるんだよ。僕の育った時代が違うんだ。かつて音楽はとても誠実で、クリエイティヴだった。今はコンピューターで、ベッドルームで1人で作れるので、狭い世界だ。人間的な要素がない分、人間がもたらす美しさやマジックが足りないんだ。
Q:新作のリリースや今後計画していることがあれば教えてください。
N:ジャーニーにはまだたくさんの可能性が残っていると信じているよ。最新作が正しいレーベルの元でリリースされるようにすごく努力したんだが、果たしてそうなったのか、今もまだわからない(苦笑)。『Frontiers』をめぐる裁判も続いている。レーベルとの話は弁護士に任せてて、僕はそこらへんの会話には関わってなかったんでね。で、(訴訟の)内容にも興味がなかったんで、弁護士が半年くらい関わっていたんだが「どうにもならない。君たちが自分でやってくれ」と言われ、関わることになり、結局、(『Freedom』は)BMGとやることになった。BMGは今の時代のColumbiaだ、君たちみたいなアクトに向いている、と言われたんだ。その選択は間違ってはいなかったと思うが、もう少しウェブサイトに予算をかけたり、アップデートに力を入れ、自分たちでチケットを売るようなことも出来たんじゃないかと思うんだ。レーベルは所詮レーベルだ。機能していないも同然だ。どんなに良いアルバムだろうと、リリースするだけ。出してすぐに結果が出なきゃ、そこまでだ。かつて、僕らがいたCBSは本物のレーベルだった。ジャーニーみたいなバンドを他には契約しなかった。EW&Fも彼らだけ。似たようなバンドを2つは契約しなかった。でも今は違う。レーベルとしての誠実さなんて、もうないんだ。今は、インターネットでアーティストが自分でヒットさせ、何百万のフォロワーがつけば、レーベルは大事にする。でもかつての本物のレーベルの時代は、アーティストが作ったものの味方になって、アーティストのために仕事をしてくれた。そんな時代はもう終わったんだよ。またそれが戻ってきてくれれば良いなと思う。僕らの旧譜は今、とても順調だ。『Greatest Hits』の新たなアナログのセールスが、1700万枚を超えたばかりだ。これは、新しいファンがダウンロードではなく、アナログ盤を買ってくれているということだ。僕自身、ダウンロードは好きじゃない。ミュージシャンにちゃんと金が支払われないということ以上に、音が良くないんだ。CDはまだいい音だよ。古いCD、カセットテープもいい。アナログもいい。でもダウンロードはすべてが圧縮されて、自分たちのアルバムじゃないみたいだ。『Freedom』をラジオで聴いた時、すごい!と我ながら思ったんだ。さすがのボブ・クリアマウンテンのミックスだった。ところがダウンロードで聴いたら最悪の音で「どうしちゃったんだ?」と思ったよ。
Q:最後に、ジャパン・ツアーに向けての意気込みと、日本のファンへメッセージをお願いします。
N:ニール・ショーンだよ。君たちの美しい国をまた訪れるのを本当に楽しみにしている。日本にはずっと戻りたかったよ。本当に大好きな国なんだ。昔からずっと。ジャーニーとして、これまでで一番のライヴになることを約束するので、一緒に楽しもう。みんなの笑顔に会える日が待ち遠しいよ。ありがとう。
-
JOURNEY ニール・ショーンとジョナサン・ケインから、日本のファンに向けてメッセージ動画が届きました!!2024.07.16