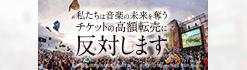JOURNEY/ジャーニー

NEWS 最新情報
-
JOURNEY ジャーニー、結成50周年記念の 日本ツアーが大阪から開幕!2024.10.20
※セットリスト・曲名には触れておりません。
開演予定時刻とほぼ同時に客電が落ち、ニール・ショーンが姿を現す。ひとりギターをかき鳴らし始めると、それがこの夜の始まりの合図だった。短いソロを弾き終えると、そのままショーンのギターからブライトなアルペジオが奏でられる。続いてアーネル・ピネダが最初のフレーズを歌い出すと、アリーナは一気にジャーニーの色に染まった。
ジャーニーの結成50周年を記念したツアー“フリーダム”、日本公演は秋の大阪からスタートした。オープニングから人気曲が披露され、アリーナとスタンドを埋め尽くしたファンは歓迎の意を表して大きく手を上げる。2007年に加入し、すでに17年も在籍するピネダは、今や押しも押されもせぬバンドのフロントマンだ。短い髪でさわやかな出で立ちの彼は、とにかくアクティヴ。曲の間奏ではステージ上手でソロを弾くショーンに絡んだかと思えば、次の瞬間には踵を返して下手に走り、観客を煽る。ステージで飛び跳ね、オーディエンスとのシンガロングを指揮する。アッパーな曲では、つねに笑顔を絶やさない。そんな彼が発する陽のエナジーで、アリーナ中にハッピーな空気が充満する。
この日は音響も際立っていた。ショーンがフルピッキングでこなす速弾きは音が明確に粒立ち、ギターを交換するたびにその個体が持つ個性を浮かび上がらせる。ディーン・カストロノヴォのドラムは、キック音をいたずらに強調させない。これを強くするとドライヴ感が増して勢い付く反面、ジャーニーの特徴であるメロディー、ハーモニーをスポイルさせてしまう。カストロノヴォの技術でそう演奏したところもあっただろうが、とにかく歌を聴かせることを最優先したバランスで整える。会場のAsueアリーナ大阪はスポーツアリーナであり、いわゆる“箱鳴り”は期待できない。ここでの公演の際はベースの音が埋もれてしまうこともあるが、今日はその存在を明確にし、アンサンブルを下支えしていることがはっきりとつかみ取れる。サウンドクルーは、良い仕事をした。今後の横浜、東京公演もコンサートホールの会場ではないが、ライブを楽しみにしている人は、この点にも期待してもらって構わないだろう。

このあとも公演が控えているので詳述は避けるが、セットリストには黄金期のナンバーが惜しげもなく並ぶ。結成50周年を迎えたとはいえ、'75年のデビューからしばらくは鳴かず飛ばずの状態だった。そんな彼らが成功への扉を開いたのは、“あの声”と出会ったこと。ボーカリストのスティーヴ・ペリーが加入して、新たなラインナップで発表した'78年の4th『インフィニティ』が初のプラチナディスクを獲得。ここで、“ジャーニーの型”が確立した。以降はそれを深化させ、'81年に今も最高傑作と称される『エスケイプ』が世に放たれる。しかしそれは、“ジャーニーの型”から逃れられない呪縛の始まりでもあった。ハードなサウンドとメロディアスな楽曲の上に、雑味なく透き通るようなハイトーンのボーカルが乗る。それが、“ジャーニーの型”。その点において、ペリーは重要人物であった。だが'83年の『フロンティアーズ』と、それにともなうツアーを終えるころからメンバーとの関係が悪化して活動は休止。それから10年の時を経て復活するも、長くは続かなかった。
その後、新たなシンガーにスティーブ・オージェリーが加入する。オージェリーはそれまで大きな成功を得られていなかったが、ペリーと近しいタイプのシンガーで、ジャーニーにマッチした。その証拠に在籍した8年間は定期的にツアーを行い、オリジナル・アルバム2作に参加。彼は良い仕事をしていたが、喉の不調が原因でバンドを離れてしまう。
ジャーニーは後任にイングヴェイ・マルムスティーンのバンドにも在籍していたジェフ・スコット・ソートを迎えるが、上手くはいかなかった。ハイトーンのボーカルがあれば、それでいいというものでないことが、この一件で明らかになったのだ。ソートの加入が実を結ばなかったことで、バンドは“ジャーニーの型”を守ることこそが生命線であると再認識した。


新たな後任探しは困難を極めたがある日、奇跡が起こる。ピネダが在籍していたバンドが、ウェブサイトにジャーニーのカヴァーをアップしていた動画が偶然、ショーンの目に留まった。それをきっかけに実施されたオーディションを経て、正式に加入が決定。フィリピンのローカルバンドのシンガーに過ぎなかったピネダはシンデレラストーリーを駆け上がり、世界的バンドのシンガーとして今、大阪のステージに立っている。
ショウはとにかく「ジャーニーのライブであるなら、この曲は演奏して然るべし」といったラインナップが並ぶ。ピネダはその声で、ジャーニーを今に存在させている。セットリストのなかで数曲、ほかのメンバーがリードボーカルを務める曲もある。それはかつてペリーが歌った曲であるのだが、彼らが歌っても全体の流れに澱みはない。たとえほかのメンバーに歌える力量があったとしても、“ジャーニーの型”から外れたタイプのボーカルであれば、その機会は用意されなかったことだろう。だからこそ、そのパートで違和感を覚えることはなく、むしろ良いアクセントになっていた。
後半は“これぞ!”なナンバーが、次々と飛び出した。硬軟交えながら、まさに怒濤の展開である。終盤に差し掛かっても、今のジャーニーの声に乱れはない。来日直前にブラジルで行われた音楽フェス「ロック・イン・リオ」に出演して、ピネダへの批判がSNSで渦巻いたとニュースになった。そのステージを現地で見たわけではないので直接の比較はできないが、この日の彼のボーカルには問題を感じなかった。中音域はふくよかで、高音はしっかりと伸びている。その印象が最後まで変わらなかったことは、強調しておきたい。
彼らはバンドの歴史のなかで、いくつかの奇跡と巡り合っている。ひとつめの奇跡は、“あの声”との出会い。ふたつ目の奇跡は、“新たなあの声”を発掘できたこと。そして3つ目の奇跡は、この夜に目にした。それは結成50周年を迎えたベテランバンドでありながら、全盛期のクオリティを保ったまま、フルスケールのショウを完遂したことだ。ジャーニーはここに集まったオーディエンスが求めているものを、なにひとつ欠くことなく提供してステージを終えた。アリーナをあとにする多くの観客が浮かべる満足気な表情が、それを物語っていた。

(取材・文/カワサキマサシ)
(写真/田浦ボン)